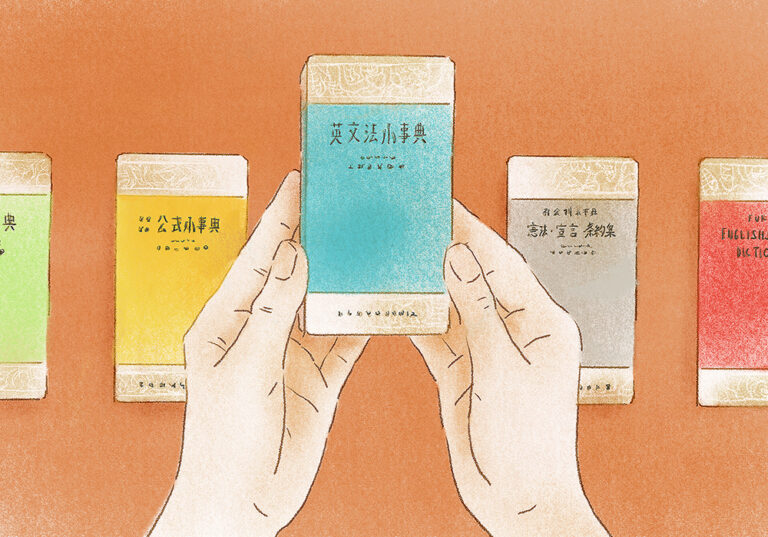
月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。
金沢の福音館へ行ったときに、私は「職業」を選んだのです。出版という仕事を選んだのです。後に僕は大学で時々教えるようになりましたけれども、3年生ぐらいの人たちに「あなた方は就職をするんですか? 就社をするんですか?」と聞くことがあります。「就職と就社はすごく違うんだよ、職業を選ぶことは生きることにつながるんだよ」と伝えるために。
今ここにいる皆さんは、就職されたんですか? 就社をされたんですか? 福音館書店に来られたということは、出版という仕事、職業を選ばれたわけです。それを自分で切り開いていかなくてはならないですね。
金沢では、佐藤喜一から編集は全部任せると言われて、「小辞典」(*1)を作ることになりました。しかし、編集のことなど何にもわからないので、ぼろぼろの机の前に座って、編集とは何をどういうふうにしたらいいのかなと考えました。そして、印刷工場へ行きました。そこの工員さんに校正の仕方を教えてもらったり、活字のことを教えてもらったり、印刷のことを教えてもらったり……私は現場で、自分で学びました。
製本もそうです。製本屋さんへ行って、どういう仕組みで本が造られているのかを見ながら、用語を教えてもらい、現場で技術を学びました。当時の福音館にはガイドブックもマニュアルもなく、校正の仕方を記した紙が1枚あったきりなんです。
しばらくしてから、『執筆・編集・校正・造本の仕方』という本をダイヤモンド社がお出しになって、それを読んで少し編集のことがわかるようになりました。美作太郎先生(みまさか たろう・*2)がお書きになった本です。美作太郎というのはすばらしい編集者で、新評論社の社長をしていらっしゃったんです。私は東京へ出て美作先生にお会いしたときに、「先生のあの本で私は編集者になれました」と言ったら、大喜びしてくださいました。
小辞典は通信販売だったので、編集の仕事をする一方で、伝票を書いて、荷造りをして、郵便局へ持っていって発送する、ということも最初は全部ひとりでやっていました。3か月間ほど、小さな倉庫の中で荷造りばっかりしていたこともあります。道を間違えたかなと思ったけれど、途中で引き返すことはしたくなかったから、辛抱して、そういう仕事もやりました。
さて小辞典ですが、これは小辞典文庫というシリーズで、1冊目は『中学数学公式集』(1950年)というものでした。2冊目からは全部私が編集していました。『物理小辞典』『生物小辞典』、あるいは『当用漢字小字典』『世界史小事典』などがあり、学者の方々に書いていただきました。一番評判になったのは『西洋文学小事典』(1954年)です。これは、桑原武夫先生(くわばら たけお・*3)に監修をしていただいたもので、実際に原稿を書かれたのは、ユニークな評論家の多田道太郎さん(*4)たちです。
多田道太郎、鶴見俊輔(*5)というのは、京都大学人文科学研究所にいた、本当におもしろい若手の研究者だったのですけれども、そういう方にお手伝いいただきました。小辞典文庫は中学生向け、高校生向けですけれども、辞典ですから、専門家が見ても「うん」と納得するようなものを作ろうと思って、素人でしたけれども、編集を一所懸命やりました。
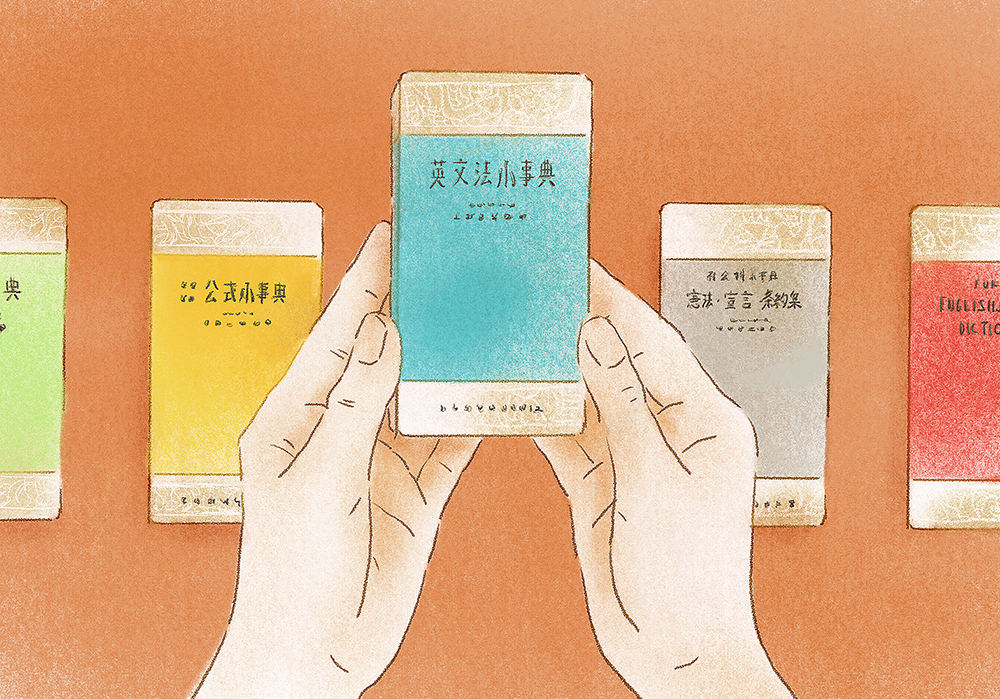
実物ができますと、宣伝しなくてはなりません。売らなくてはなりません。その売り方について、福音館の経営者の佐藤喜一という人は、すばらしい商売のセンスの持ち主でした。そもそも、私はそれを感じたものですから、この人と仕事をしようと思ったのですけれども、佐藤喜一が何をしたかというと、実物見本を全国の中学校へ献本したのです。実物を、です。小さな本ですから、封筒に入ります。小辞典を1冊と、広告用のチラシと、振替用紙と、時にはポスターを入れ、さらにPRのために小辞典を採用している学校の一覧を作成して封筒に入れました。封筒の宛名書きもやらなくてはいけませんが、これは外部の方にお願いしました。今のように宛名印刷はできませんから、全部手書きです。
封筒に入れる作業は夜なべ仕事でした。福音館の小売(本屋)が店じまいをした後で、店員として働いている方とか、その家族を動員して、封筒に詰めて、ホチキスで全部留めて、翌朝リヤカーに載せて、自転車でリヤカーを引っ張って、金沢の中央郵便局へ持っていくわけです。何回も往復しなければなりません。新制中学(*6)は全国にたくさんありますから。
中学生向けの理科の小辞典なら理科の主任の先生宛に、数学なら数学の主任の先生宛に出すわけです。1週間から10日ほどしますと、振替や郵便でぼつぼつ注文が来る。それを私が毎朝郵便局へ取りに行って、持って帰って、整理をして、どこそこの学校が何冊という注文を全部複写伝票に書きます。その複写伝票の中の送品の紙を持って、倉庫へ行きます。少し離れたところに倉庫がありました。古いバラックみたいな倉庫でしたけれども、そこで今度は品出しをして、注文書に従って数をきちんと数えて、荷造りをして、また郵便局へ持っていくのです。
その間、私は伝票を書きながら、「ああ、こんなにたくさん注文していただいてありがとうございました」と思いますし、何とかもっと注文してもらえる方法はないのだろうかと考えたり、どういう先生がこれを注文してくれたのだろう、どんな子どもたちの手に渡るのかなと考えたりしながら荷造りをしておりました。読者を考えるということは、そのとき以来、私の習性になったかもしれません。
そのうちに、小辞典もだんだん部数が増えていきますと、学校の先生が、いちいち郵便振替で送金するのは面倒なものですから、出入りの本屋さんに、小辞典を注文したいということで注文される。本屋さんは、それを東京なり、大阪なりの取次店に問い合わせるわけです。
ところが、東京や大阪の大きな取次店は、福音館なんて出版社は聞いたことがない。探しても、どうしても見つからない。ある時、取次店の営業の方が、金沢に福音館という本屋があった、あそこかもしれないということで、電話をかけてきました。「あの小辞典を出しているのはお宅ですか?」「はい、うちです」というやりとりがありました。「実は書店からの注文があるのだけれども、出荷をしてくれませんか?」という話でした。
こんなうれしいことはありませんから、天にも昇る心持ちで「すぐ送ります」と言って、東京の取次店へ送りました。ついに取次店から書店さんを経由して読者の手に渡るのです。
佐藤喜一という人は、高等小学校(*7)を出て、名古屋の星野書店に小僧さん(*8)として入って、そこでたたき上げた人です。そして番頭(*9)にまでなって北陸を担当しているときに、たまたまクリスチャンでありましたから、カナダ人宣教師に請われて、金沢の福音館という本屋のマネジメントを任されたわけです。
もともと聖書や賛美歌集を売る小さな店だった福音館を、佐藤喜一は北陸でも指折りの書店にしたのですが、立地条件も非常によかった。当時は目の前に旧制の第四高等学校(*10)がありました。旧制高校の学生はものすごく本を読みますから、その学生さんが買いに来てくれて、書店としてもたいへん安定した商売をしていました。
ずっと後のことですけれども、ある会合に出たとき、新聞社の方に私が名刺を出したら、「金沢の福音館?」と言われたのです。「どうしてご存知ですか?」と尋ねたら、「僕は四高の卒業生だ」と。「出世払いで、福音館にはまだ借りがあるんだ、申し訳ない。親父さんはまだ元気にしている?」とおっしゃったので、印象に残っているのだなと思いました。
そういう、お客様と書店との関係性みたいなものがあった。これも、商売のセンスの現われ方のひとつです。
イラスト・佐藤奈々瀬
*1 小辞典=福音館小辞典文庫。縦12.5×横7cmの非常に小型の辞書。『英文法小事典』『数学公式小辞典』『化学小辞典』『生物小辞典』『日本史小辞典』『図画小事典』『基礎 経済用語小事典』など、様々な種類があった。 *2 美作太郎(1903-1989) 日本評論社で活躍した編集者。後に新評論社を創設。 *3 桑原武夫(1904-1988) フランス文学者。登山家としても知られる。京都大学人文科学研究所の教授などを務めた。 *4 多田道太郎(1924-2007) フランス文学者。京都大学人文科学研究所の教授などを務めた。桑原武夫と共同研究を行った。 *5 鶴見俊介(1922-2015) 哲学者、評論家。『限界芸術論』(ちくま学芸文庫)、『思想をつむぐ人たち』(河出文庫)、『思い出袋』(岩波新書)、など。桑原武夫の推薦により、京都大学で一時期教鞭をとった。 *6 新制中学校とは、1947年施行の学校教育法に基づく中学校のこと。これを機に中学3年間も義務教育となった。 *7 高等小学校は、戦前まで存在していた教育機関。義務教育の尋常小学校を卒業した後、勉学を継続したい者のための学校として位置付けられていた。 *8 小僧=商店などで働く年少の従業員 *9 番頭=商店などで業務を取り仕切る従業員の頭、リーダー *10 旧制第四高等学校は、金沢市にあった旧制高等学校。現在の金沢大学の母体のひとつ
▼次の回へ▼
▼前の回へ▼
▼第1回から読む▼


来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話


来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!