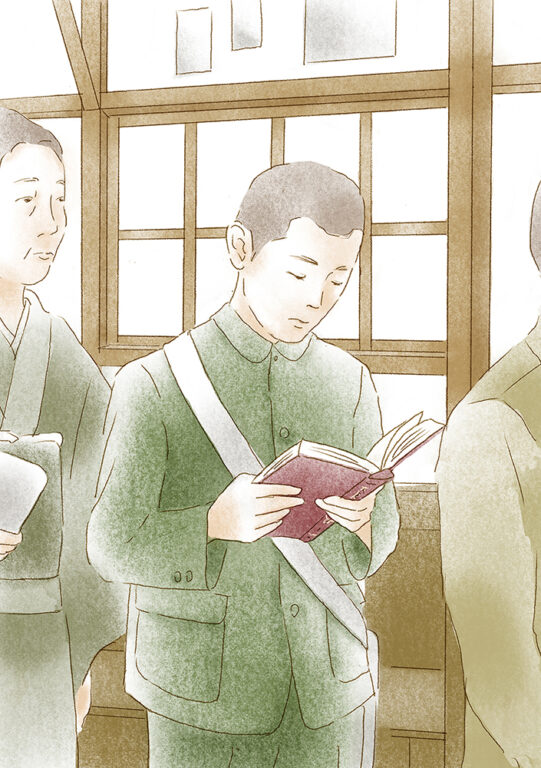
月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。
徳冨蘆花とトルストイのかかわりが印象に残っていたものですから、古本屋で『大トルストイ全集』(中央公論社)を見つけたときに、「どうしても読む!」と私は思いました。うちへ飛んで帰って、親父に「あの全集をどうしても読みたいんだ、買ってくれ」と言うと、親父も割合に本が好きだったから、「いいよ」と。
翌日、一緒に古本屋さんへ行きました。僕は親父と買い物に行ったのは、後にも先にもあのときだけです。どんな着物を着ていたかまで、今も覚えています。2人で22巻を風呂敷に包んで、持って帰りました。
その晩から私はトルストイを読み始めました。最初に読んだのは「戦争と平和」です。平和なんてわかりません。戦争のことは経験から少しはわかります。
もちろん買い出しにも行かなくてはいけないし、親父の仕事の手伝いみたいなこともしなくてはいけないので、買い出しの汽車の中、私はデッキに座り込んで「戦争と平和」を読んでいました。切符を買うのに2時間ぐらい並んで立っているときも、立ったまま読んでいました。もう朝から晩まで読んでいました。あの本には、生きるということと、死ぬということが、見事に書いてあります。私は、そこで少し光を見たような気がしました。
『大トルストイ全集』のだいたい八割ぐらいまでは読みました。「復活」や「アンナ・カレーニナ」も読みました。「幼年時代」(*1)は、とてもおもしろかったです。ごく初期の作品です。
私は、人間がどう生きればいいのか、何のために生きるのか、そういったことをトルストイの本でほんの少し手がかりを得ました。いずれにしても「生きる」ということを、私はそのときから考えられるようになったんです。
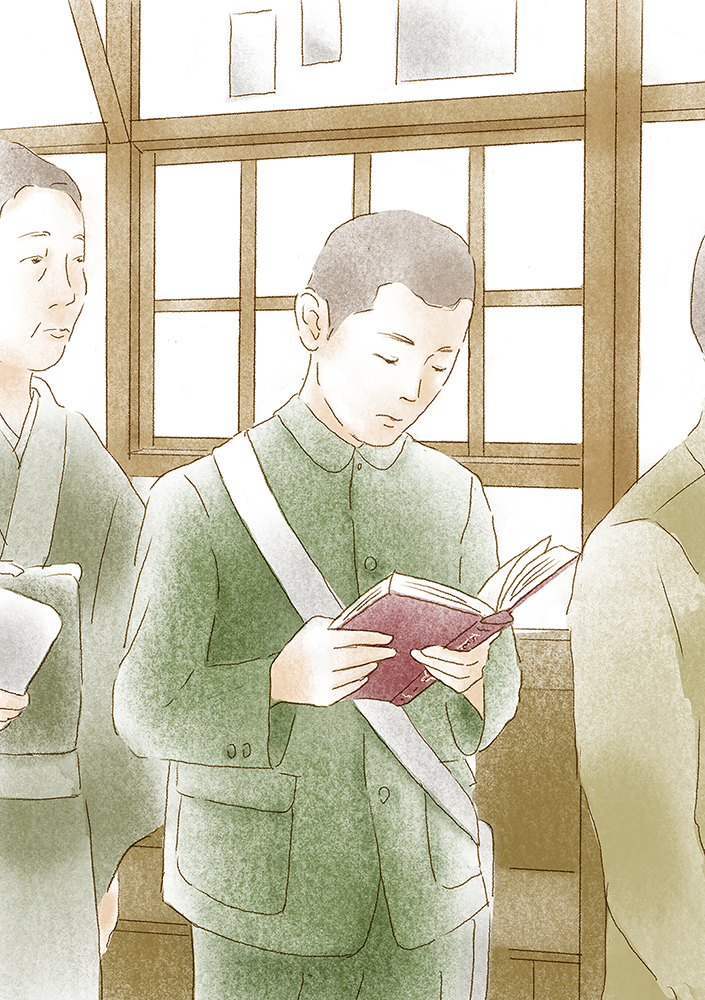
今、私が仕事をしているのも、その延長線上なんです。生きるために仕事をしているんじゃなくて、生きること自体が仕事をすることとつながっていて、何のために生きるのかと考えると、何のために仕事をするのか、ということになってくる。私にとっては、いまだに重要な問題なんです。たぶん僕は、自分が死ぬときまで「生きるとは何か」と考え続けるんだと思います。
子どもの本を作る編集者になってからも、「生きる」ということが、いつも私のテーマでした。そんなに難しい哲学的なことを考えているわけじゃありませんけれども、兄たちが3人とも死んでいますから、死んだその人たちのことは、いつも頭の中にあるんです。そして、その人たちが生きていたら何をしただろうか、何を考えただろうかと今でも思います。みんな20代で死んでいるわけですからね。とにかく兄たちだけじゃなくて、本当にたくさんの人が死んでいるんです。その人たちの代わりに生きるという気持ちではなく、生きるということが、その人たちが残した宿題ではないかな、と思うこともあります。
そういう戦争体験が、私のすべての仕事につながってくるんです。
敗戦の翌年(1946年)に、家から歩いて行ける大学が同志社だったので、旧制大学の予科へ入りました。東京の大学にも行きたかったけれど、そのころは東京も大阪も焼け野原でした。京都は焼けなかったので大学が残っていました。
予科の入学式のときに、初めてキリスト教の聖書の朗読だとか、賛美歌だとか、礼拝だとかを知りましたが、そのときはまだぴんとこなかった。でも、同志社でキリスト教に出合ったことは、それもまた「生きる」ということを考える上で、大きな手がかりのひとつになりました。
同志社で私が最も多くを学んだのは、「学生を丁重に扱え」という新島襄(にいじま じょう・*2)の遺訓です。新島襄は同志社を創設した人ですが、その遺言の中にそれがあります。
実際、先生方は学生を丁重に取り扱ってくださった。朝、道でばったり先生に会って「おはようございます」と立ち止まってあいさつすると、そのころは帽子をかぶっていらっしゃる方が多かったんですけど、帽子をちょっと脱いで「おはよう」とちゃんとあいさつを返してくださる。学生をひとりのジェントルマンとして大切に扱ってくださったんです。それは身にしみて感じました。
一番印象に残りますのは、卒業のときの出来事です。在学中に旧制大学から新制大学になったものですから、私は5年間大学に行ったんですけれども、もう親父も死んでいましたし、兄たちも亡くしていましたから、最後の年はアルバイトをしていました。けれども、どうしても授業料が払えなくなりました。卒業試験は合格したという通知をもらったので、学生部へ行って、これこれこういうことで授業料が払えません、外で働いて半年したら必ず払いに来ますからと言ったら、学生部の人たちが「わかりました、待っています」と。「卒業証書をどうしますか」と聞くから、「払えないから預かっておいてください、必ずお金を持って取りに来ますから」と言って、私は卒業をしました。
それから半年間、金沢の福音館書店で働いて、授業料を持っていきましたら、「卒業証書は預かってあります」と言われて、もらって帰ってきました。そのくらい、ちゃんと学生を信用してくれました。
もうひとつ印象に残っていることは、予科の2年生のときだったかな、就職のことが心配になって、政治学を教えていらした岡本清一先生(*3)に、友達も一緒でしたけど、キャンパスの中を歩きながら「就職というものはどう考えたらいいんですか?」と質問をしたんです。
そうしたら、岡本先生はしばらく黙って歩いていらしたんですけど、やがて、ぱっと私の顔をご覧になって、「松居君、大学は学問をするところです」とおっしゃった。つまり、「自分で学び取りなさいよ」と岡本先生は言っているんだなと思いました。
私は、そのときから卒業するまで、「教えられる」んじゃなく、できるだけ自分で学んでいこうと考えました。実は、「教えられる」ことにはかなり反感をもっていたんです。「戦争中に教えられたことは何だったんだ」という気持ちが、戦後もずっとありましたから。先生方が嘘を教えたとは思いません。しかし、戦争中に教えられたことは、敗戦と同時にひっくり返ってしまった。私はそれ以来、「教えられる」ということにあまり期待をしなくなりました。
イラスト・佐藤奈々瀬
*1 『幼年時代』は、トルストイが自身の幼年時代を描いた自伝小説。
*2 新島襄(1843-1890) 明治時代の教育者。幕末に米国へ密出国し、キリスト教の洗礼を受ける。帰国後、京都に同志社英学校(後の同志社大学)を創設した。
*3 岡本清一(1905-2001) 政治学者。同志社大学教授、法学部長も務めた。
▼次の回へ▼
▼前の回へ▼


来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話


来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!