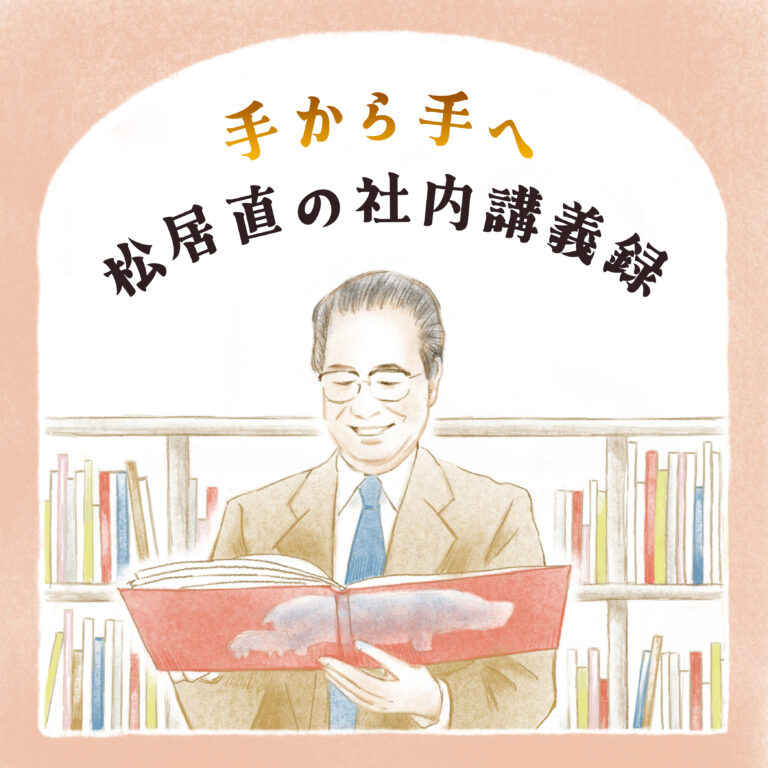
月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。その言葉と本作りの姿勢は、子どもの本の出版社として歩む福音館書店の根底に今もありつづけます。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。子どもの本にかかわる、すべての人たちへ贈るメッセージです。
今日は月刊絵本「こどものとも」創刊のころの話をしようと思います。そこから、いわば本格的に “子どもの本の福音館書店” という歴史が始まるんです。「こどものとも」を創刊しましたのは、1956年の4月のことです。
初期の「こどものとも」がどのようにして編集されたかについては、私の最初の本である『絵本とは何か』(日本エディタースクール出版部 1973年/現在「ちくま文庫」より刊行)の「第四章 絵本編集のなかから」に詳しく書いてあります。「なんとしてもまったく新しい月刊の絵本を作ろう」というのが出発点でした。
当時、日本で刊行されていた子供向けの月刊誌は、保育の教材としての絵雑誌がほとんどです。1956年のころに一番よく出ていたのは「キンダーブック」(フレーベル館)で、それから「よいこのくに」(学習研究社)、「チャイルドブック」(チャイルド)、「ヒカリノクニ」(ひかりのくに)、至光社から「こどものせかい」も出ていました。そういった月刊の幼稚園、保育園向けの保育雑誌と言われるものが主流だったわけです。
子ども向けの月刊誌が、こんなにたくさん出ている国はほかにはありません。1956年のころに、月刊で絵雑誌のようなものを出していた国は、チェコスロバキアとイランだったと思います。イランはパーレビ朝の時代で、近代化を幼児教育から進めようということで、子どもの本に一所懸命力を入れていました。子どもの本を作る王立の機関がありましたけれども、革命後にその機関はなくなりました。それまでは、イランはとてもよい絵本を作っていました。もう一度そういう絵本がイランに生まれるといいなと、私は思います。
日本で月刊の絵雑誌の口火を切ったのは婦人之友社で、自由学園をお作りになった羽仁もと子さんが1914年に主筆になられて、「子供之友」という月刊の絵雑誌をお出しになったのです。羽仁もと子さんは婦人解放や新生活運動の中で、特に家庭教育を非常に大切にされて、そのために雑誌「婦人之友」をお出しになった、新しい思想を持った方でした。そして、日本ではそういった新しい考え方に基づいた子どもの本がないということで、「子供之友」をお出しになったんです。
「子供之友」の思想的なよりどころについてお話したいと思いますが、皆さんはエレン・ケイを知っていらっしゃいますか? 婦人解放と新しい教育について重要な本を書いたスウェーデンの人です。日本で訳されているものに、『児童の世紀』(冨山房)と『恋愛と結婚』(新評論)があります。「二十世紀は子どもの世紀である」という言葉を聞いたことがありませんか? これはエレン・ケイの言葉です。1900年、ちょうど20世紀が始まる前年にスウェーデンで出版した『児童の世紀』の中に書いている、大変に有名な言葉です。
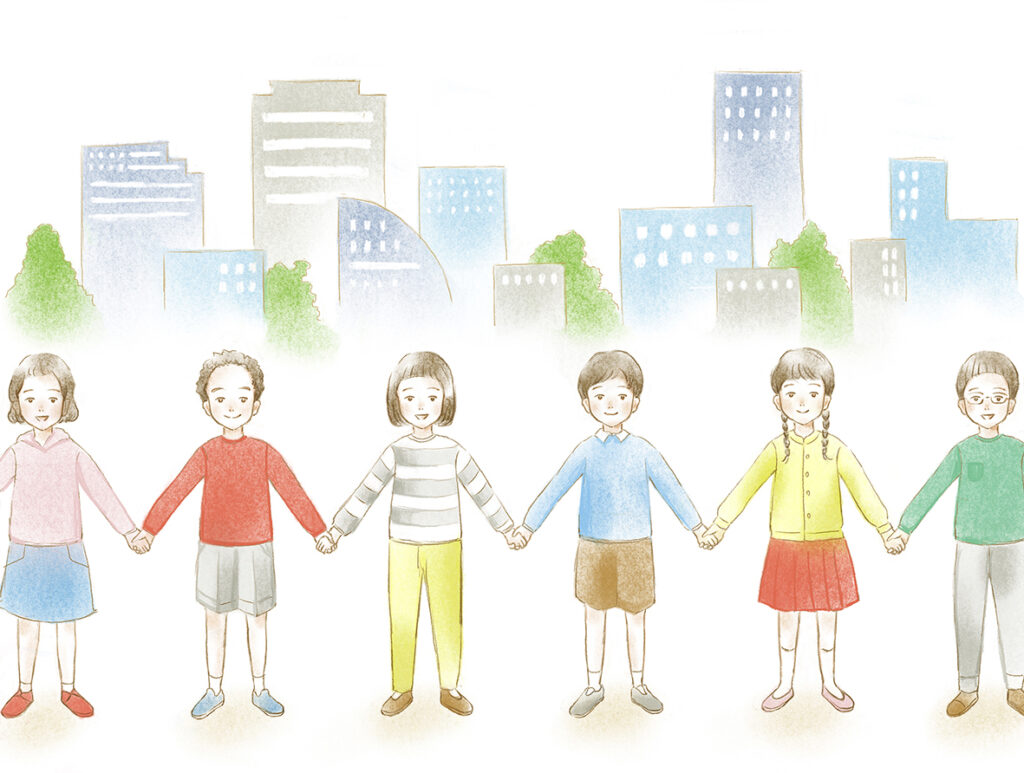
この『児童の世紀』にどんなことが書かれているか、その一端ですけれどもご紹介してみましょう。小野寺信さんと小野寺百合子さんの共訳です。
「わたしはいまだかつて、よく教育された人間を見たことがない。わたしの見たのは、いくらかの甘やかされた人間、一部の追い立てられている人間、それにたくさんの訓練された人間で、よく教育された人間ではない」
「子どもは、その学校に対して従順であり、その仲間に対して忠実であり、後ではその大学と学生クラブに対し、またその公務に対し、従順であるように教えられる。子どもがそれよりも先に学ばなければならないのは、その良心に対し、その正義感に対し、その心の衝動に対して正直であれということなのに」
これを、今から100年以上前に言っているのです。
もうひとつあります。
「教育者は子どもに、『ほかのみんながやる』ことの模倣は決してしないように助言しなければならない」
僕は大賛成です。
「いまの学校では、どんな結果を生んでいるであろうか? それは脳の力の消耗であり、神経の衰微であり、独創力の阻止であり、進取性の麻痺であり、周囲の真実に対する観察力の減退である」
今でもこの通りです。
さらに、こんな言葉もあります。
「今日では家庭は学校の予備校以外の何ものでもなく、ここで育つ青少年はサービスを受けることに慣れて、サービスを返すことを知らず、常に受けるばかりで与えることを知らない。すでに人びとは、いまの『利己的で思いやりのない』青少年に驚きの目をみはっている。かれらはあらゆる機会に無遠慮に年長者の前にのさばり出るし、かつては青少年の麗しい態度となっていた丁寧さがなく、乱暴な不行儀が目立つ」
本当に、あまりにぴしゃぴしゃと当たるものですから、もう怖いぐらいですけど、その影響を受けた人がエルサ・ベスコフで、あの『ペレのあたらしいふく』という、エレン・ケイの考え方を見事に表わしている絵本を作ったんです。
羽仁もと子さんは、こういう考えを何とか日本に伝えようということで「子供之友」という絵雑誌をお出しになった。
私は「こどものとも」を出すときに、ちゃんとお断りをしたんです。羽仁もと子さんの長女の説子さんが「日本子どもを守る会」の会長をしていらっしゃって、そのお仕事をちょっとお手伝いしていたことがあります。そのとき説子さんに「『こどものとも』という誌名で、月刊の絵本を出したいと思います。もし婦人之友社でお出しになるということがあるといけないし、婦人之友社が商標登録していらっしゃるということもあるかもしれませんから、一度そのことについてご相談をしたい」と申し上げました。すると、説子さんはすぐに婦人之友社に掛け合ってくださって、「婦人之友社では登録をしていません。今のところ再刊をする考えは婦人之友社にはないようですから、お使いになったらいいでしょう」と言ってくださったのです。こうして「こどものとも」という誌名をいただいて、商標登録をし、4月号から出すことになりました。
「こどものとも」は、1冊の本の中にひとつの物語が載せてある。そして、ひとりの絵描きさんが全部の場面を描いている。そういう月刊の絵本は、日本にはありませんでした。世界中のどこにもなかった。私は絶対に真似だと言われない本を作りたいと思ったものですから、この、1冊の本で、ひとつのストーリーで、ひとりの画家が絵を描いて、そしてペーパーバックで出すという未曽有の企画を立てたんです。売れませんでしたけどね(笑)
*出版社名の記載のないものは福音館書店刊
イラスト・佐藤奈々瀬
▼次の回へ▼
*
\こちらもおすすめ/


来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話


来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!