
1955年にオランダで生まれ、今年70周年を迎えた「うさこちゃん」。そんな「うさこちゃん」とブルーナ作品の魅力について、「くまのぼりす」シリーズの翻訳を手掛ける中野百合子さんにうかがいました。東京子ども図書館の研修生を経て、都内の図書館に勤務後、現在はロンドン市内の公共図書館で働く中野さん。日本とイギリスで図書館員として働いた経験も踏まえて、語っていただきました。
──ブルーナシリーズの翻訳はこれまで、石井桃子さん、松岡享子さんという、児童文学界のレジェンド的なおふたりが手掛けてきました。続く3人目の翻訳者として、中野さんが大切にしたこと、気をつけたことがあれば、お聞かせください。
自分自身も小さい頃から「うさこちゃん」シリーズを楽しんでいたのと、図書館員になってからも子どもたちと読んできた作品だったので、大きなプレッシャーを感じましたが、とにかく、ブルーナさんが作った世界を壊さないように、というのを心がけました。たくさんの方が長いこと親しんできた「うさこちゃん」シリーズの続きとして、違和感なく収まるようなものにしたいと思いました。
──『ぼりすと こお』、『ぼりす そらをとぶ』に関しては、松岡さんとの共訳という形で翻訳をされています。共訳については、松岡さんからご連絡があったとうかがいました。
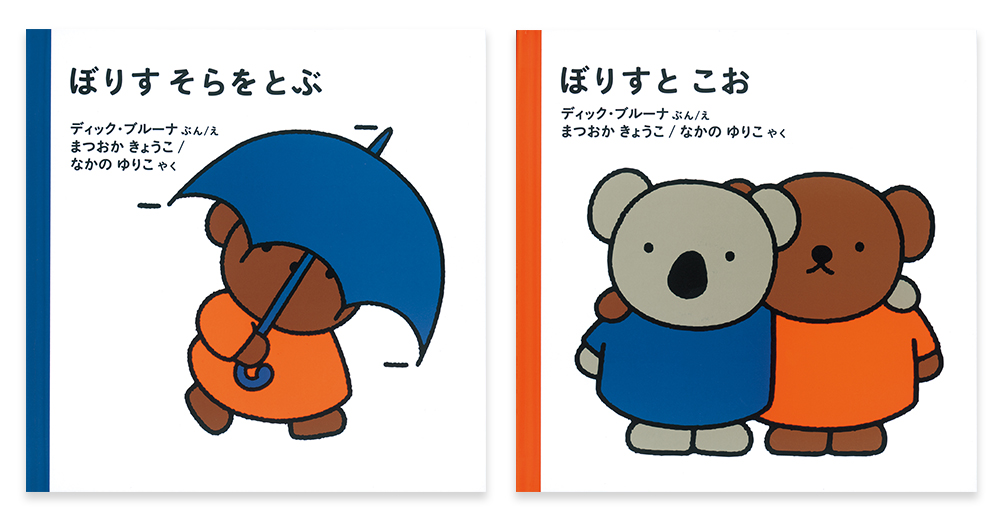
松岡先生には、2003年度に東京子ども図書館で研修生をさせていただいて以来、ずっとお世話になっていました。ブルーナさんのシリーズは、世界的にも、自分の中でも、大きい存在で、自分が関わることになるとは思っていませんでしたので、共訳をしてみないかとご連絡をいただいた時は、本当にびっくりしました。プレッシャーはもちろんありましたが、松岡先生にこれまでの恩返しをしたい、という気持ちでお引き受けしました。
──松岡さんとはどんなやりとりをしながら訳を進めていったのでしょうか。
当時は松岡先生がご闘病中だったので、細かくいろいろやり取りしたわけではないのです。先生のご体調がよろしい時に、わたしがお送りした原稿を先生のお嬢さんが読み上げて、松岡先生がコメントされる。その様子を録音して送ってくださるという形でやりとりしていました。録音された松岡先生からのメッセージを聞いて、私が原稿を調整してメールでお送りし、編集者の方とも相談し、気になるところがあれば先生に質問するという形で進めていました。
松岡先生は、細かいことはあまりおっしゃいませんでしたが、最初に、「子どもは物語を読むのだから、ひとつひとつの場面がきちんとつながって、お話が流れるようでないといけません」と言われました。また、ブルーナさんの本の原文は、文章が全部4行になっていて、文章のおしりが出たり入ったりしないできれいに整っているんです。松岡先生も、それをなるべく崩さないように訳文を作ってきたので、そこはできるだけ守ってほしいというのも言われました。
まず最初に『ぼりすと こお』をほとんどご自身で翻訳されて、「こういう感じでやるのよ、わかるでしょう?」みたいな感じで訳文が送られてきました。それを参考に『ぼりす そらをとぶ』を訳し、2作を同時に練っていきました。訳文を聞きながら、「こういう言い方(言葉)はどうかな」などとアドバイスをくださることもありました。たとえば、『ぼりす そらをとぶ』の中で、わたしが「そらのたび」と訳していた箇所は、「『くうちゅうりょこう』っていうのもいいかもね」と提案してくださいました。
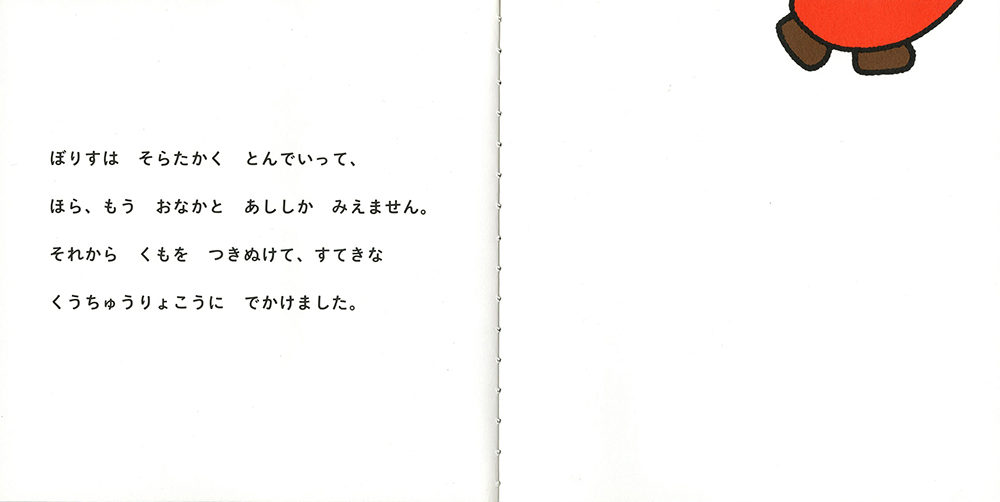
そうして松岡先生から届く音声に、ときどき面白いコメントが入っていることもありました。例えば、『ぼりすと こお』の中で2人が一緒にスープを食べて仲良くなる場面があるのですが、松岡先生が「どこでも同じだね。同じ釜の飯を食って仲良くなる」とつぶやいていたんです(笑)。文章のやり取りではなく、松岡先生のコメントをそのまま録音して送ってもらえたおかげで、先生から直接ご指導を受けているような臨場感を感じることができたのは貴重な体験でした。
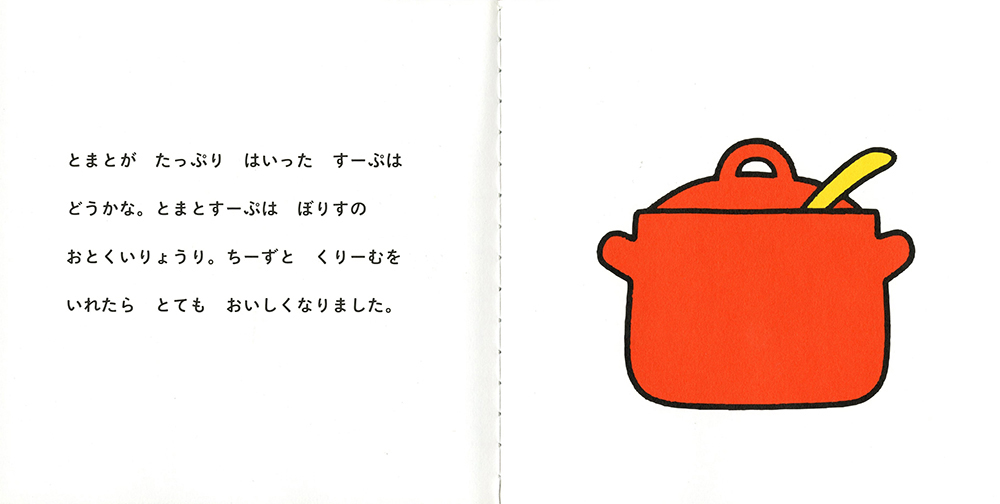
──実際に翻訳をされてみて、難しかったところや、印象的だったところがあれば、ぜひ教えてください。
ブルーナさんのシリーズは、言葉がとてもシンプルなのと、すべてのページが4行で、2つ目と4つ目の文章で韻を踏んで詩の形をとっていることで説明的な文章がなく、意味を掴むのが難しいと感じることはありました。
なんとか正確に意味を掴もうとして絵をじっくり見ているうちに、大きく変わらないように見える登場人物の表情も、喜んでいる時と、悲しんでいる時で、微妙に口の開き具合が違うなど、それまでは気が付かなかった発見もありました。
松岡先生との共訳で印象的だったのは、『ぼりすと こお』で、こあらの「こお」と出会う場面です。実は、こおの「ぼくは いま せかいじゅうを たびして いるんだよ」という言葉は、原文にはありません。
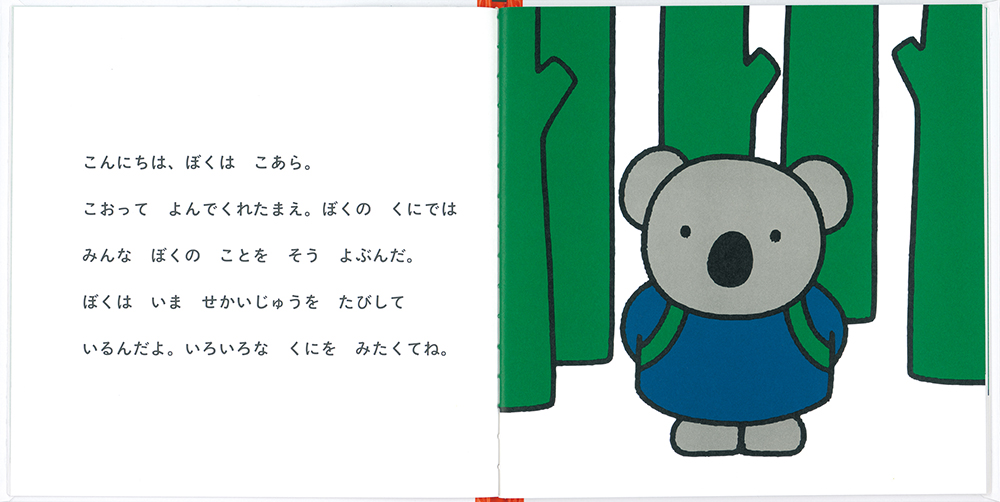
これは松岡先生がどうしても入れたいとおっしゃったところでした。最後にこおが理由なく旅立ってしまうところが、とてもさみしいと感じた。また、突然こおがいなくなってしまったら、子どもたちが戸惑ってしまう、というのがその理由でした。当時担当してくださった編集の方とも相談して、確かに、読んでもらった子どもたちが安心してお話を楽しむためには、こおがぼりすのもとを去る理由があった方がいいということで、この表現が入ることになりました。
子どもの本を翻訳する上で、原文に忠実に訳すということは基本ではあるけれども、子どもたちに物語を届けるものとして、こういうことをやらないといけない時もあるということを、『ぼりすと こお』の翻訳を通して教わりました。
──「ぼりす」にはどんな魅力があると感じていますか?
うさこちゃんのシリーズ含め、ブルーナ作品に共通していることだと思いますが、登場人物がみんな優しくて、温かくて、愛らしい。それはぼりすも同じです。
一方で、うさこちゃんは家族と一緒のお話が多いですが、ぼりすは一人暮らしをしていて、自立している印象があります。途中からは友だちの「ばーばら」と一緒に住んでいますけど、自立して生活していることで、こおのような知らない人も受け入れて、一緒に食事を作って……と、物語の幅が広がっていくのではないかなと思います。
──中野さんは翻訳者として「ぼりす」シリーズに関わっていらっしゃいますし、図書館で子どもたちに読む立場も経験されています。作り手と読み手の両方を経験された上で、ブルーナシリーズの魅力はどういうところにあるとお感じでしょうか。
うさこちゃんシリーズをはじめとして、ブルーナさんの作品はどれを読んでも本当におもしろいし、読後の満足感があると思います。短いお話の中にドラマもあるし、安心感もある。そういうところがブルーナシリーズの魅力だと思います。
子どもに本を読む立場から見ると、石井先生、松岡先生が訳したブルーナさんの文章は、やっぱり本当に心地よくて温かいと思います。特に、石井先生が訳された初期の作品は、歌のような一定のリズムがあります。わたしは『きいろいことり』を小さい子に読むのが好きなのですが、それは、心地よい響きがわらべうたみたいに感じるからだと思います。
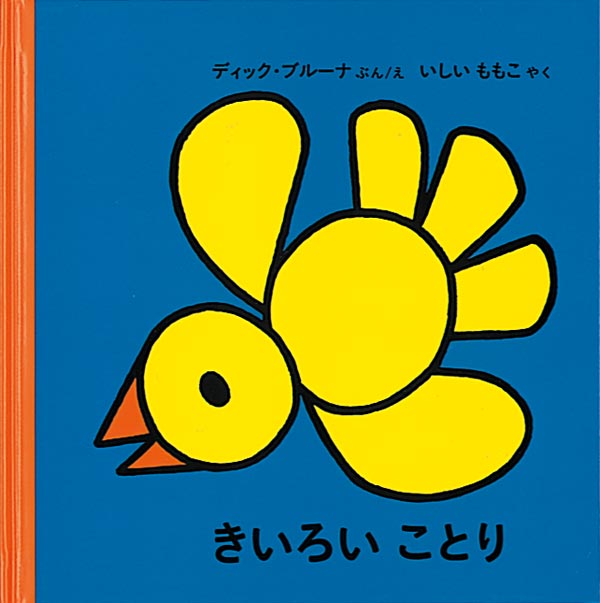
昨日ブルーナさんの展覧会に行ってきたのですが、展示のビデオの中で「子どもたちの心に何かを残せたら、自分の作品はきちんと役割を果たせたと感じる」というようなことをブルーナさんがおっしゃっていました。私も、よい本から得られる喜びは一時的なものではなく、その子の心に長い間残るものだと思うので、子どもに本を読む立場として、そういう本を選びたいと思います。それができたら、今度はわたしが図書館員としての役割を果たせたなと感じます。翻訳者としても、子どもの心に残り続けるかというところは大事にしたいと思います。
──子どもたちに絵本を読んでいる時に、印象的なエピソードがあれば、ぜひ聞かせてください。
日本で児童図書館員として働いていた時のことなのですが、2才くらいの小さい子どもたちに『きいろいことり』を読むと、全体に不思議な一体感が生まれると感じていました。小鳥に連れられて、実際に子どもたちと一緒に農場を歩いているような感覚というか。先ほど言った、リズムのよい言葉のおかげなのか、聞いていても気持ちがいいし、読んでいても気持ちがいいから、自然とその場に一体感が生まれるのかもしれません。
最近だと、イギリスは9月から新学期が始まるので、『うさこちゃん がっこうへいく』を読みました。先生がうさこちゃんたちにお話をしてくれる場面で、「ぼくの学校でも、先生が帰る前にお話してくれるよ」ってつぶやいている子がいて、かわいかったです。うさこちゃんに親近感を持って聞いているのだな、と思いました。
──中野さんが、ブルーナシリーズの中で特にお好きな作品はありますか?
これは難しいです! 子どものころは『うさこちゃんと うみ』の貝殻が並ぶきれいな場面が大好きだったし、面白い名前と、双子への憧れもあってか、『ぴーんちゃんとふぃーんちゃん』も好きでした。大人になった今は、『おかしのくにの うさこちゃん』が好きです。というのも、疲れて「もうこのまま怠けて暮らしたい」と思ってだらだらしかけた時に、「そんなふうに していたら ぶくぶく ふとった なまけものの うさぎになってしまう」っていうところが、ふと口をついて出てきて助けられているので(笑)。
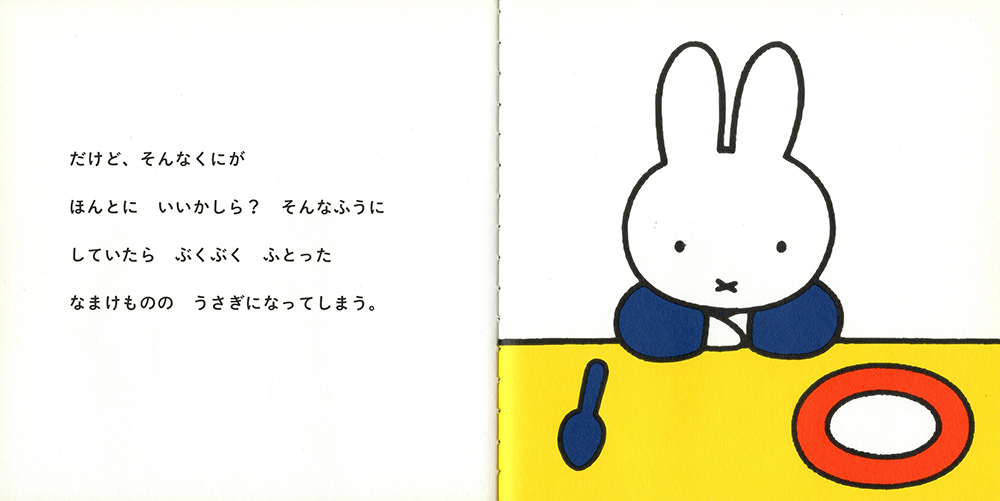
あと、わたしには姪と甥がいるので、ふわこさんやうたこさんなど、おばさんが出てくるお話も好きです。姪や甥ができてからは、うさこちゃんとその周りにいる人たちを、自分の家族と重ね合わせて楽しむようにもなりました。うさこちゃんが、おじいちゃん、おばあちゃんと仲良くしているのを見ると、微笑ましくなります。また、松岡先生と共訳した『ぼりすと こお』ももちろん、思い入れのある、忘れられない大切な作品です。
──うさこちゃんシリーズがはじめて翻訳出版されたのは1964年、イギリスと日本で同じ時期に刊行されたと聞いています。日本では、翻訳されてから60年経った今でも、絵本が読み継がれていますし、キャラクターとしても人気がありますが、イギリスではどのような存在なのでしょうか。
イギリスでも「うさこちゃん」シリーズ(英語版は“Miffy”)は読み継がれていると思います。ただ、イギリスはやっぱり自国の絵本や児童文学が大切にされているので、そもそも翻訳ものが日本ほど多くありません。“Miffy”シリーズも日本ほど図書館にずらっと並んでいるわけでもないですし、シリーズの中で手に入らない作品もたくさんあります。
とはいえ、身近なところにあると、しっかりと手に取られるシリーズであると思います。今働いているイギリスの図書館で、“Miffy”シリーズが古くなっていたので、抜けていた絵本も含めて手に入るものをすべてそろえました。手に取られるかなと思って見ていたところ、割とよく借りられています。子どもがすごく喜んだと親御さんから聞くこともあります。わらべうたの会に来てくれる子の家に、次の赤ちゃんが生まれると聞いたら『うさこちゃんと あかちゃん』を読んだり、小学生に上がる時期の子どもたちが来たら『うさこちゃん がっこうへいく』を読んだりして子どもの反応を見てみましたが、どれも、よく聞いていました。イギリスでも、子どもたちと一緒に、うさこちゃんのシリーズを読み続けていきたいなと思います。
*
\うさこちゃんとミッフィーのちがいとは?/
うさこちゃんシリーズ
特設ページ
▼▼▼
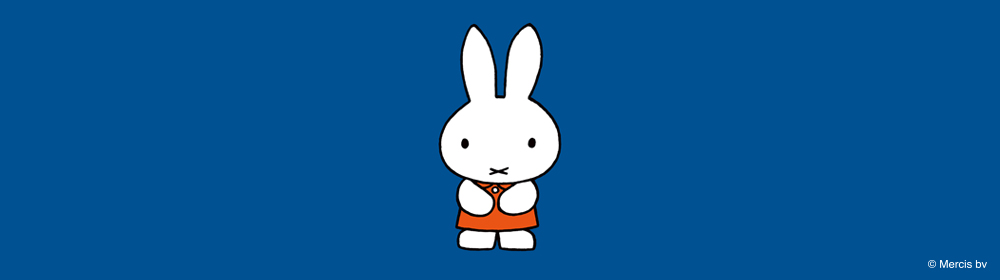


来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話


来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!