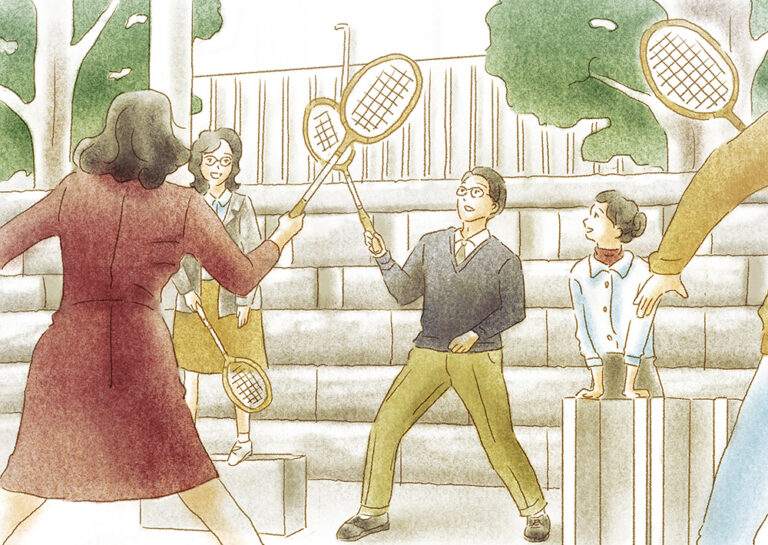
月刊絵本「こどものとも」を創刊し、多くの子どもたちに愛される絵本や童話の数々を送り出した編集者・松居直(まつい ただし)。この連載では、松居が2004年9月から2005年3月にかけて福音館書店の新入社員に向けて行った連続講義の内容を編集し、公開していきます。
取次店から小辞典の注文が来るようになって、それがだんだん増え、かなりまとまった注文が来るようになると、いちいち東京や大阪へ送っていたのでは手間もかかりますし、大変だから、東京に品出し所を作りました。
多田製本(*1)がまだ神田の三崎町にあったときにお願いをして、間借りする形で品出し所を作って、そこから品物を出すようにしたのですが、それでも間に合わない。というのは、金沢の印刷所、製本所がもう限界に達していて、まかないきれなくなっていたのです。出荷に費用がかかるということもあって、思い切って東京へ出ようということになりました。そのときに、「株式会社福音館」から出版部門を「有限会社福音館書店」として独立させたのです。
そして、社長以下6人で東京へ出てきました。私は金沢で事後処理を全部やって、一番最後に東京へ出ました。その頃、神田の三崎町に一般住宅が売りに出ていましたから、それを社屋にするために手に入れました。出版社ですから、神田にいる方がよいだろうと考えたのです。神田だったら、取次店は集品に来てくれますから。三崎町の社屋が整うまでのあいだ、会社は杉並区清水町に居を構えた佐藤喜一の自宅に間借りしました。1階の和室2間の襖を外して、ともかく机と椅子を並べました。
──今はもう、都内に会社があって倉庫もあるという出版社はほとんどありませんけれども、現在の社屋を巣鴨(文京区本駒込)に建てたのにも理由があるのです。これを建てた頃は、山手線の内側までは取次店がトラックで集品に来たのです。とてもよいところにこの土地が見つかって、本当によかったと思いました。
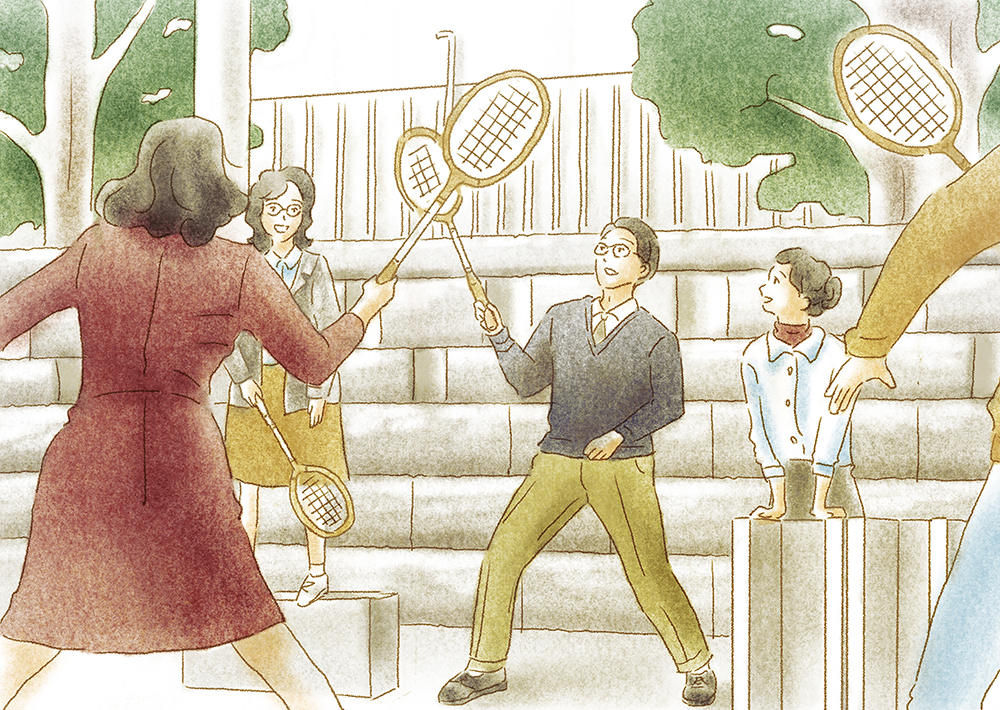
そんなことがあって三崎町に本社ができまして、そこから品出しをするようになりました。東京に移ってからは、書店訪問と受注活動と、本屋さんの店頭に福音館の本がどういうふうに並んでいるかを見るということを徹底的にやりました。営業の人が全国の本屋さんを回りました。
当時は北海道、沖縄はあまり行きませんでしたが、それ以外は本当に全部回りました。営業の人が本屋さんを回って、その本屋さんが前に注文してくださった小辞典が棚に並んでいますから、それをきちんと整理をして、時にはほこりを払って、何が抜けているかを調べて、「これだけのものが抜けています、ぜひ追加注文をしていただきたい」ということで注文書をいただいて、本社へ持って帰ります。それを本社でまとめて、取次店に「これだけの注文があります」と出す。取次店は、注文品として来ているものですから、喜んで扱ってくださる。
そのように私たちは、いつも自分で本を作り、自分で売るということによって出版活動をしていこうと考え続けてきたわけです。
東京へ進出してきて、社員も5、6人いましたから、杉並区の天沼に社員寮を作りました。私もそこにいました。私の家族も含めて、多いときは20人ぐらいいたかな。普通の家で、そこでみんなが共同生活をしておりました。新しい社員の方も次々入ってきました。
今江祥智(いまえ よしとも・*2)君は、あそこに寝泊まりしていたんじゃないかな? 薮内正幸(やぶうち まさゆき・*3)君もそうです。私の連れ合いが全部食事の世話をしていました。
私の子どもたちは、いつも薮内君に絵を描いてもらっていました。ウサギの絵を描けとか、鳥の絵を描けとか。薮内君は一所懸命、子どものご機嫌をとって描いてくれていました。
小辞典から、やがて辞書、それから学参物に移っていって、福音館は参考書の出版社になっていきます。教材的な英語のピクチャーカードなど、オリジナルなものをいろいろ作っていたんですけれども、この分野はだめだと私は思った。
小辞典でもかなりよいものを作って、それなりに認められてはいたんです。平凡社での辞書を編集している人が、「福音館の小辞典ってよくできているね」と言ってくれたこともあります。英語の辞書もかなりいいものを作りました。だけど、英語の辞書になると研究社や三省堂や岩波書店がすでにあるわけです。国語の辞書なら角川書店などが、いっぱい作っていらっしゃる。そういう出版社はちゃんと自分のマーケットがあって、本屋さんにも棚のスペースを持っているからいいけれど、われわれは新参者ですから、それがない。とても学参物では生き残れないと感じました。
また、学参物というのは、どんなに工夫をしたとしても、教科書や教育の枠の中でしか仕事ができないのです。辞書の作り方にしても、参考書の作り方にしても、大枠があって、少し工夫して少し差が生まれる、という程度です。もっとオリジナルな、もっと新しい、誰も真似ができないような学参物を考えても、売れませんから、出せません。
安定度はあるのだけれども、発展の可能性が限られています。だからそこへ入っていっても、先行の出版社の後塵を拝するだけになります。 そういったことを考えるにつけ、学参物の将来に疑問をもつようになりました。今は売れているから、別に危機を感じているわけではないけれども、先を考えたら、いずれ行き詰まりが来るだろう、何か別の道がないだろうかと思っておりました。
もっとオリジナルなものをやりたいと考えて、ずっと出版界を見てみたときに、一番手薄だったのが子どもの本の分野だったのです。
イラスト・佐藤奈々瀬
*1 多田製本は、現在板橋区にある製本会社。当時は東京の千代田区三崎町にあり、福音館の小辞典の製本を担当していた。後に絵本専門の製本会社に移行。
*2 今江祥智(1932-2015年) 児童文学作家。著書に『ぼんぼん』(岩波書店)『優しさごっこ』(理論社)『くいしんぼう』(文研出版)などがある。松居直は同志社大学の先輩にあたり、松居の誘いにより一時期は福音館書店の社員でもあった。
*3 薮内正幸(1940-2000年) 絵本作家、動物画家。著書は『どうぶつのおやこ』『しっぽのはたらき』『どうぶつのおかあさん』『野鳥の図鑑』など多数。『冒険者たち ガンバと15ひきの仲間』(斎藤惇夫 作/岩波書店)のシリーズの挿絵も手掛けている。高校卒業と同時に福音館書店に入社し、図鑑や絵本の絵を担当。他社からの依頼も増えていき、1971年にフリーランスに転じた。
▼次の回へ▼
▼前の回へ▼
▼第1回から読む▼


来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話


来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!