
読み聞かせは子どもにいいらしい。こんなことを耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。でも……絵本がいいってほんと? この連載では、さまざまな角度から、絵本と子どもの関係を解き明かしていきたいと思います。
慶應義塾大学で、子どもの言語獲得や思考力について研究を行ってきた、今井むつみ先生へのインタビュー後編では、幼児期の「読み聞かせ」で養われた「ことばの力」が、小学校以降にどうつながっていくのか、うかがいました。
──幼少期から養われていく「ことばの力」と「思考力」は、小学校以降にどうつながっていくのでしょうか。
「ことばの力」と「思考力」は、小学校以降の学力の基盤になると考えています。例えば、学力に大きな影響を与える「読む力」について。「読解力」の基盤になる要素はいくつかあるのですが、ある言葉がもつ複数の意味から、文脈に合ったものを選べるかどうかというのも、「読解力」の有無につながっています。
ほとんどの言葉は、ひとつの典型的な意味だけをもっているわけではなく、複数の意味をもっています。例えば、「切る」という動詞。「切る」には、実にいろいろな意味があります。「はさみで切る」「水を切る」「シャッターを切る」……全部違いますよね。
「ことばの力」で大事なのは、文脈ごとに、その言葉がどの意味で使われているかを自分で判断できることです。読むのが苦手な子は、なかなかそれができません。知っている言葉だったとしても、自分の理解している意味以外で使われてしまうと、思考が止まってしまいます。
「はさみで切る」の「切る」は知っていても、キャベツを洗ってざるで水を切っているときの「切る」はわからない。文脈に合わせて別の意味をあてることができないので、思考が止まってしまうか、すでに知っている意味を無理やり当てはめて、意味が取れなくなってしまいます。特に、文章の核となる「動詞」の場合、文脈に合わせて意味を理解できないと、文全体の意味が取れない。それが、「読解ができない」ということにつながっていくわけです。

また「読解力」だけでなく、子どもがつまずきやすい「数」の理解にも、実は「ことばの力」が大切になってきます。「数の言葉」はとても抽象的です。例えば、「イチ(1)」という言葉。「赤い消防車」は見えても、「赤」という概念そのものが見えないのと同じで、「1個のリンゴ」は見えても、「イチ」と言う概念そのものは見えないですよね。
数の理解って、言葉の理解の延長なんです。人間は「もの」に注意がいきやすいので、「イチ」という概念を「もの」と切り離して理解するのは、とても難しい。子どもが「数」を理解しようとしたときに、まず「もの」と切り離すところでつまずきます。
次につまずくのは、「イチ」を、「基準としてのイチ」としてとらえる必要が出てきたとき。「基準としてのイチ」というのは、いくつかのものをまとめて「イチ」とするときなどに使うもので、例えば、1㎝は5㎝の何分の一ですかっていうことを考える場合は、5㎝を「イチ」としているわけです。算数という文脈では、「基準としてのイチ」の理解が必要になってきます。
──「基準としてのイチ」は、分数や比で出てくる「イチ」の使い方ですね。
はい。「イチ」の概念って、分数、割り算、割合、比、速度の計算……そういうものの基本になっています。だから、「イチ」の意味が理解できていないと、割り算や比も理解できない。苦手としている子が多い割り算や比などの分野は、そのほとんどが「イチ」の理解に絡んでいると思います。
──算数の土台になる「イチ」の理解にも、「ことばの力」が大事になってくるということですね。
ここで注意してほしいのが、大人がもっている「イチ」の概念を、子どもの頭の中にそのままインプットすることはできないということ。「イチ」という言葉を理解するためには、結局は子ども自身が「イチってどういう意味なんだろう」って、自力で考えるしかありません。
例えば、モノの数を数えるときの「イチ」しか知らない子に、「子どもが3人います。これを『イチ』とします」と言っても、どうして3人なのに「イチ」なの? と思いますよね。小学校3年生で割り算を習うわけですけど、3で割るってどういうことなのか、本当に「イチ」が理解できていないと、わからないわけで。
──「基準としてのイチ」を子どもが理解できるようになるには、何かきっかけなどがあるのでしょうか。
「イチ」という言葉を使ういろんな場面を、たくさん経験することだと思います。
子どもに何かを教えようとするときに、わかりやすい事例をひとつ挙げたら理解できると考えている大人が多いと思いますが、それは誤解です。ひとつの事例で理解できることは、ほとんどありません。
そもそも大人は、「イチ」とか「右」とか、そういう概念が抽象的だということすら理解していない。だから「右は、お箸を持つ手ですよ」とか言ってしまいます。でも、「右」という言葉は、「お箸を持つ手」を意味するわけではないですよね(笑)。
とは言っても、「右」そのものを言葉で説明するのも難しい。「右」「左」というのは完全に相対的なもので、まず視点の中心が自分にあるのか、自分以外のものにあるのかがわからないと決まらない。どちらの視点かが決まると、前後が決まる。そして前後が決まって初めて、左右が決まります。
「イチ」も「右」も子どもが自分で発見していかないと、本当には理解できない言葉なのです。
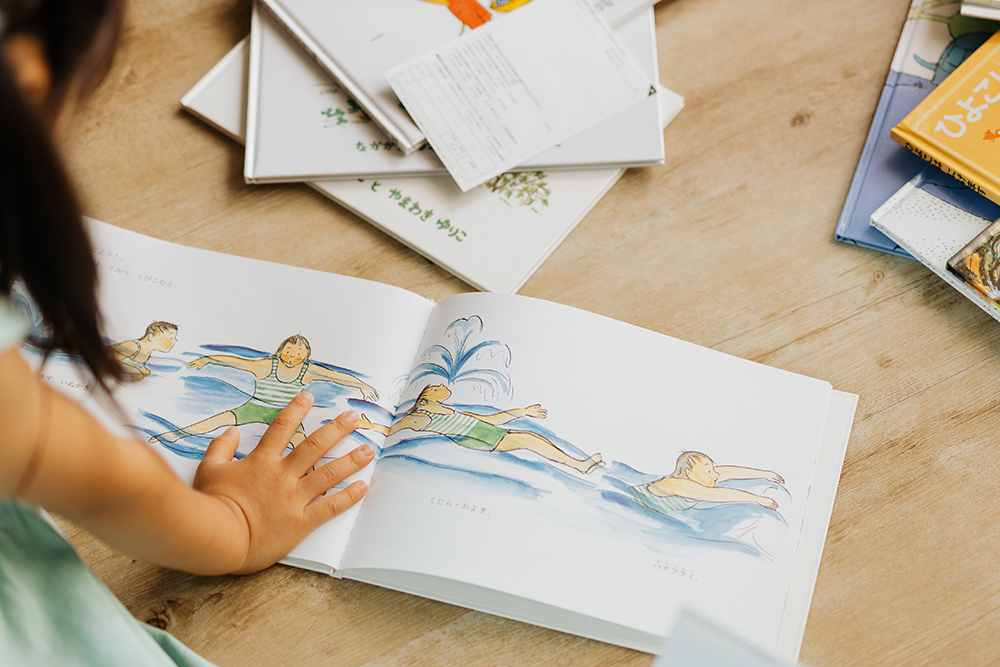
──子ども自身がいろんな経験をしながら、考えていくことが大切なんですね。
正解がない今の世界を生き抜いていくためには、今ある材料や状況、情報、自分の知識を総動員して、最もよい結論は何なのかということを考える「思考力」を身につけることが大切です。経験の中からエッセンスを見つけて考えていくと、もちろん間違うことも多いけれど、それを自分で修正しながら理解していく。その過程が必要なのです。
絵本の読み聞かせも含め、幼少期からそういった経験を積み重ねていくことで、言葉を理解する力も、考える力も一緒に伸びていきます。
子どもたちには、状況に即して複数の可能性を考えながら、最善の結論を引き出し、それを柔軟に評価できる力をつけていってほしいですね。
(まとめ:とものま編集部)
▼今井先生へのインタビュー 前編を読む▼
*
\専門家に聞く 絵本と子どもとの関係/


来月は これ読もう!

絵本がいいってほんと?

絵本の選びかた

わたしの限界本棚

あの人の ほっとするとき ほっとするもの

母の気も知らぬきみ

えほんとわたし

親の知らない 子どもの時間

こどもに聞かせる 一日一話


来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!

来月は これ読もう!